Shoot ‘Em Up Kitは、初心者でも簡単にシューティングゲームを作成できるゲームクリエイションツールです。 直感的なドラッグ&ドロップインターフェースを使って、わずか数秒で基本的な2Dまたは3Dのシューティングゲームを作成することができます。また、照明、カメラ、物理演算、シェーダー、パーティクルエフェクト、AIなどの要素も細かくカスタマイズできるため、より複雑なゲームも作成可能です。完成したゲームはスタンドアロンのexeファイルとしてパブリッシュでき、販売やコミュニティとの共有が可能になります。
どんなゲーム?
Shoot ‘Em Up Kitは、プログラミングやスクリプトを一切必要とせずに、直感的なドラッグ&ドロップ操作でシューティングゲームを作成できるツールです。プレイヤーキャラクター、敵キャラクター、武器、背景などを選んで配置するだけで、すぐにゲームが作れてしまいます。その一方で、光源、カメラ、物理演算、シェーダー、パーティクル効果、AIなどの要素も詳細にカスタマイズできるため、より高度なゲーム制作も可能です。作成したゲームはスタンドアロンのexeファイルとしてパブリッシュでき、販売やシェアができます。ゲームエンジンを持たない個人やアマチュアでも、簡単にシューティングゲームを作れるツールとして注目されています。
プロモーション動画が見つかりませんでした。Shoot ‘Em Up Kitの評価は?
Shoot ‘Em Up Kitのユーザーレビューでは、まだ開発中の段階ではあるものの、初心者でも簡単にシューティングゲームが作れる便利なツールだと高い評価を得ています。多くのレビューでは、ゲームの仕組みや機能が分かりやすく、手順さえ覚えれば短時間で作品が完成できると好評です。一方で、チュートリアルやドキュメンテーションが不足しているため、複雑な機能を理解するのが難しいという指摘もあります。また、バグやクラッシュ、UI の使いづらさなどの問題点も挙げられています。ただし、開発チームが積極的にコミュニティとのコミュニケーションを取り、随時アップデートを行っていることが高く評価されています。
DLCはある?
現時点で、Shoot ‘Em Up Kitにはダウンロードコンテンツ(DLC)はありません。ただし、将来的にはユーザーが自作したコンテンツをワークショップ経由で共有できるようになる予定とのことです。今のところは、ゲーム内の素材やアセットを使って自作するか、外部のツールで作成したものを取り込む機能が主です。
Shoot ‘Em Up Kitは無料で遊べる?
Shoot ‘Em Up Kitは有料のゲームクリエイションツールで、Steamで購入する必要があります。無料でダウンロードして使用することはできません。
マルチプレイはある?
Shoot ‘Em Up Kitには同PC上でのローカル1人用プレイ機能はありますが、オンラインでのマルチプレイには対応していません。ただし、作成したゲームをスタンドアロンのexeファイルとしてパブリッシュすれば、その作品をオンラインでシェアしたり販売したりすることは可能です。
対応言語は?
Shoot ‘Em Up Kitのメインの言語は英語ですが、日本語をはじめとする複数の言語にも対応しています。ユーザーインターフェイスや各種メッセージ、マニュアルなどが日本語化されているため、日本語を母語とするユーザーでも問題なく利用できます。
動作環境は?最低要件
- OS: Windows 7 以降
- CPU: 2GHz以上のデュアルコアプロセッサ
- RAM: 4GB以上
- GPU: DirectX 9以上対応のビデオカード
- ストレージ: 2GB以上の空き容量
比較的低スペックなPCでも動作するため、多くのユーザーが手軽に使えるツールとなっています。
PC GAME NAVI編集部レビュー
Shoot ‘Em Up Kitは、プログラミングやスクリプト知識がなくても直感的に操作できる、初心者向けのシューティングゲーム制作ツールです。ドラッグ&ドロップでキャラクターや武器、背景などを配置するだけでゲームが作れるため、短時間でゲームを作り上げられるのが魅力。一方で、高度な機能を使いこなすのは難しい面もあるものの、開発者によるサポートが手厚く、徐々に機能が充実していくため、今後の進化に期待が高まります。(編集部)
Shoot ‘Em Up Kitの評価・DLC・日本語対応をまとめました
Shoot ‘Em Up Kitは、プログラミングなしでシューティングゲームが作れるゲーム制作ツールです。ドラッグ&ドロップで直感的に操作でき、短時間でゲームが作れるのが特徴です。レビューでは、初心者にも使いやすいと高評価ですが、機能が複雑なためチュートリアルやドキュメントが不足しているという指摘もあります。DLCはありませんが、ユーザー自作コンテンツの共有機能が計画されています。日本語にも対応しているため、日本国内のユーザーも問題なく使えます。


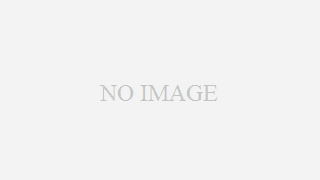






























人気記事